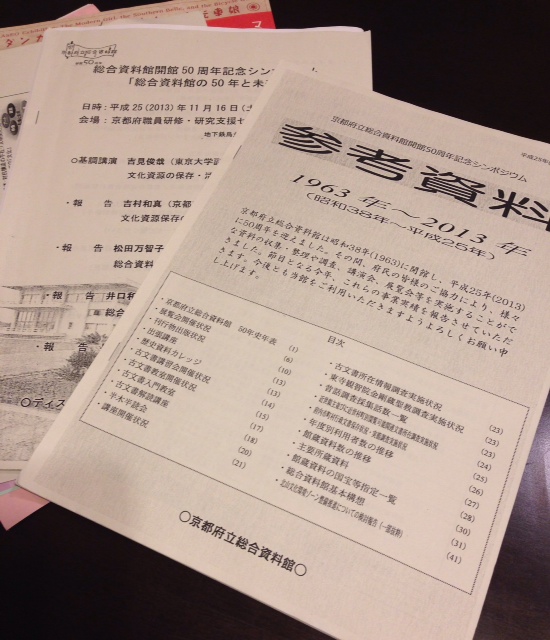牧義之『伏字の文化史:検閲・文学・出版』(2014.12、森話社)

- 作者: 牧義之
- 出版社/メーカー: 森話社
- 発売日: 2014/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (7件) を見る
版元HPはこちら(書影あり)。
ある特定の時期に、集中的に密度の高い研究成果が相次いで発表されるジャンルというものがある。例えば00年代後半から10年代にかけて急速に活発化した検閲研究は、そのような分野の一つだろう。若手研究者によるこの分野の研究蓄積が本書であり、刊行が待ち遠しい本だった。
著者のHPはこちら
検閲研究は、国内の図書・雑誌出版だけでなく、映画や、海外の事例まで入れるとかなりの数にのぼる。

- 作者: 菊池良生
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2013/04/11
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る
さて、本書の課題は「戦前・戦中期の検閲体制下における、伏字の文化記号としての意義と役割、そして文学作品への影響に関する実証的な考察である」(p.14)とされる。検閲研究のなかで本書がどういう画期的な意味を持つのか、私的な読書メモとして考えたことを書いておきたい。
検閲制度に関する歴史
本書は博士論文を元にしたもので、序章では、先行研究が整理される。検閲の研究は、江藤淳以来、占領期の研究として進んできたとされる。プランゲ文庫を活用した研究成果は、近年でも出続けている。

- 作者: 江藤淳
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1994/01/10
- メディア: 文庫
- 購入: 31人 クリック: 453回
- この商品を含むブログ (46件) を見る

- 作者: 福島鋳郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1987/12
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 実業之富山社
- 出版社/メーカー: 実業之富山社
- 発売日: 2007/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
占領期に関する検閲研究に比して、戦前・戦中の実体解明が進んでこなかったことを指摘した上で(p.20)、紅野謙介、鈴木登美、ジェイ・ルービンの各氏によって、近年、戦前期日本を対象にした注目すべき研究成果が発表されていることもあわせて紹介される。

- 作者: 紅野謙介
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2009/10/09
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 1人 クリック: 31回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
千代田図書館ある内務省委託本の調査・分析も、その一環に加えられる*1。そうするとこの4、5年は、検閲に関する研究者の反応が敏感になっているということもできそうではある。
そのなかで本書の特色はといえば、伏字を権力弾圧の結果、負のイメージを持ったキズとしてとらえるのではなく「文化記号的な使用形態」(p.23)に注目することなのだという。
「文化記号的な使用形態」というのは何なのかについて、著者は「読者が介入できる”余地”」(p.57)を対置させる。このあたりは、近年も注目されている言論抑圧に関する諸研究とは一線を画する視点だと思う。
また、かなり重要な指摘だと思うのだが、「施される字数が原文に対して非常に厳密に対応している」(p.61)ということが、伏字の大きな特徴とされる。この字数の厳密さが、逆に伏字部分の読解可能性を担保するというのである。また、伏字が黒塗りのものから白抜きの丸や四角などになっていくことも、日本人の美意識に合致する部分があったのではないかと著者は指摘する。
伏字のいろいろ
もともと伏字は、『明治事物起源』などによると、維新後に徳川慶喜の名前を隠すために使われていていたらしい。佐幕派の新聞で、慶喜を反逆者として示すことができず、遠慮から使われだしたとされる(p.32)。
伏字にもいろいろなバージョンがあった。
外国語やローマ字で埋める場合、同じ字数だけ他の符号を埋める場合、活字をひっくりかえし、ゲタの形で示したもの*2、数字を使うもの、伏字部分を余白にするもの、伏字部分を別刷にして密かに頒布するもの(!)、あえて誤字を挿入して正誤表でわかるようにするもの・・・そのほか黒塗りなどなど様々な事例が紹介されている(p.34以下)。
伏字は「無意味な記号としての役割を超越して機能していた」(p.62)とする著者は、伏字が施される理由を次のようにまとめる。
そこにあるのは、単に隠蔽に用いられただけの記号ではなく、当局に対する抵抗としての言論の仮の姿であり、当時の発行者、執筆者から読者への呼びかけの機能を仮託された意味記号でもあった。繰り返しになるが、伏字は主として発行者、あるいは編集者によって意図的に施された記号であり、検閲当局からは・・・内閲などを通して指示が反映されたものもあるが、その影響は原則的に間接的なものであり、直接的な指示による伏字化はまず行われないと考えて良い(p.63)
引用中にも出てくるが、著者が注目しているのが「内閲」という制度である。
内閲とは大正6年(1917)頃から大正末期・昭和初期までの約10年間、内務省図書課において編集者が事前に原稿を見せて修正個所の指示を非公式に受けていた制度のことである。
つまり「内閲の結果を反映する場合に用いられたのが、様々な記号形態での伏字だった」(p.98)。
しかし内閲は円本ブームを受けた出版点数の増加により、廃止せざるを得なくなり、代わって、禁止処分を受けたもので、発行者が還付願を提出して受理された場合、指定箇所を削除して発行者に還付する「分割還付」の制度が運用されていくようになる*3。
内閲と出版史の論点
本書の面白味は、例えば萩原朔太郎の『月に吠える』発行過程の分析を通じて、内務省交付本と流布本の奥付にかかれた発行日付の違いを指摘する箇所や(p.118)、発禁書の引用が許されず、与謝野晶子の詩を後年引用する際には伏字にせざるを得なかったこと(p.137)など、内閲の視点を得て、著者が出版史上の論点を描いていくところにある。
権力側の抑圧に対する、いわばしたたかな対抗策として伏字をみていく著者は、たとえば昭和11年(1936)に、全国特高課長会議で伏字一律廃止とする方針が決定されたことに注目する(p.214)。
これなどは実に面白い。
要するに自主規制に見せかけて著者や出版者が巧妙に伏字を「逆用」するので、取り締まりの効果が上がらず、逆効果を生じるからであった。だがこの方針は一時的なもので成功を収めなかったらしい。
もう一つ面白かったのは、こういう伏字が特殊日本的なものだという指摘である。
たとえば占領下、CIEに納本した出版物について、呼び出しを受けたある編集者は、婦人将校から「あなたは検閲の結果を理解していなかった」として、次のように叱責される。
すなわち、削除箇所を空字にしている。削除すべき文書を削除せず誌面を黒く塗りつぶしている、これにより、事前に検閲があったことが歴然と残っていることを厳重注意されたという。
事前に検閲があったことがバレてはならないのだから、伏字は生き延びようがない。かくして占領期に伏字は一時的に姿を消すことになったのである。
いくつかの疑問など
ただ、もとになった論文を読んだ段階でも思ったのだが、内閲の史料がないのが問題であるとはいえ、大正6年に内務省に原稿を見せる習慣が、どうやって広がっていったのだろうかというのは気になった。
完全な立証が難しいのは承知の上なのだが、p.111以下で論じられる『月に吠える』発行過程の考察(朔太郎が、当局の注意を受けて一部の作品をカットして発行せざるを得なくなったこと、それに彼が非常に憤ったことなど。)について、萩原朔太郎が内閲の制度を知らなかったのはそうだとして、なぜ発行者の前田夕暮は内務省にゲラを持っていった方が良いと判断したのだろうか。危ないと思う箇所が朔太郎の作品にあったのだろうか。文芸作家の間で内閲が一般的に知られていなかった段階だとすれば余計にその部分は知りたいと思う。
あと、雑誌と単行本の内閲の仕方が同じなのか違うのか、開始時期も一緒なのかどうかが気になるところもあった。
これは引用史料で雑誌を取り締まっているのに、「従来出版法により・・・」とあって、根拠法に「新聞紙法」の記載がない箇所があったからだが*4、法で定められていないのに運用でカバーしている部分なので、公文書等の史料にも残りにくく、まだまだ不明な部分があると思われる。いずれにせよ内閲の詳細な検討の余地はまだ残されているといえるのだろう。
もう一つ、大きな文脈におけば、内閲が行われていた時代の言論規制は、第一次世界大戦の終結と関東大震災をはさむ政党政治の時代に運用されていたことの意味をどう位置づけられるかということも気になる。これは出版史の論点として私自身も今後意識していきたいところである。
自主規制ということの意識をかなりポジティブに捉えるということは、本書の戦略的なスタンスだと思うのだが、しかしたとえば制度的な検閲よりも自主規制をよりネガティブなものとして捉える視角も、たとえばフランクフルト学派などを参照した思想系では比較的根強くあるように思われ、こういう立場と本書がどう対話していくのかも気になった。
例えば『啓蒙の弁証法』における「校訂者が自動的に行う予備検査は別にしても、原稿審査係、編集者、改作者、出版社の内外にいる代作者等々のスタッフの手によって、ある著作のテキストに加えられる審査の手続きは、その徹底ぶりにおいてどんな検閲をも凌駕している*5」というような「検閲」観との付き合い方とでもいおうか。もちろんまた一方には、加藤典洋がいうように、禁止されたものだけを祭り上げるだけでなく、合法的な範囲内で批評することの意味も積極的に捉えなおして良いという考えもあるのだが。

- 作者: ホルクハイマー,アドルノ,Max Horkheimer,Theodor W. Adorno,徳永恂
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2007/01/16
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 89回
- この商品を含むブログ (79件) を見る

- 作者: 加藤典洋
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2005/05/21
- メディア: 単行本
- クリック: 18回
- この商品を含むブログ (27件) を見る
この本を見たある方が、「おもしろそうだけど、若い人からすると伏字にはマイナスイメージとか刷り込まれていないからできる研究なのかなあ」という感想を漏らしていたが、なるほど、自主規制も表現の挫折として捉えるむきは、たとえば私が思想史の勉強を始めた頃に確かにあった*6。だからまさに新しい世代だからできた研究なのであろう。

- 作者: 鹿野政直
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1999/05/17
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 8回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
引用に『読売新聞』が多いのは、「実証的」研究を標榜する本としてはちょっと気になるところだが、それでも本書は検閲に当たった内務官僚や警察の発言などを丁寧に拾っているので、その部分を読むだけでも勉強になる。それにしても、自分より若い人のしっかりした研究成果がどんどん出始めていることに焦りを感じてしまう今日この頃ではある。
*1:内務省委託本については、千代田図書館のウェブサイトの下記を参照。http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/findbook/naimusho/
*2:布川角左衛門の『出版事典』の記述を読むと、活字を「伏せ」たときに上にくる「〓」部分を使用することが由来のようにも見える。
*3:内閲とこの制度変更については、千代田図書館が企画した浅岡邦雄氏の講演会「「戦前内務省における出版検閲【PART-2】:禁止処分のいろいろ」」でも触れられていた。詳細はこちらを参照。http://www.kanda-zatsugaku.com/080801/0801.html
*4:…と書いておいて、後になって出版法第二条但書きによって発行する雑誌、すなわちもっぱら学術・技芸・統計・広告の類を載せる雑誌に限定した議論の可能性もあるなあ…と気づいたので、誤読だったらごめんなさい(後記)。
![伏字の文化史 検閲・文学・出版 [ 牧義之 ] 伏字の文化史 検閲・文学・出版 [ 牧義之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0739/9784864050739.jpg?_ex=128x128)